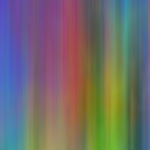○ロヒンギャ難民とは
ミャンマーのイスラム系少数民族ロヒンギャが隣国のバングラデシュに逃れ、大量の難民となり劣悪な環境下で暮らしている実態について、日本では実情が知られていないどころか、多くの人は知ろうともしないまま日常を過ごしています。
ロヒンギャと呼ばれる人々がなぜ激しい暴力によってミャンマーを追われ、命からがらバングラデシュに逃げ込んだのかも、基本的に宗教対立のない日本人には感覚として理解できない面もあります。
世界情勢に詳しい日本ユニセフ協会曰く、問題の根底はミャンマーをはじめ周辺諸国が英国の植民地だった時代にさかのぼり、仏教徒が多いミャンマーでは英国統治時代以降に入ってきたイスラム系民族のロヒンギャを自国民とは認めていなかったために、主に彼らが暮らしていた地域では長年にわたって根深い確執がくすぶり続けていました。
ロヒンギャはミャンマー軍事政権下の1980年代末期から1990年代にかけても激しい弾圧を受けバングラデシュに逃れており、国際連合難民高等弁務官事務所の仲介によってミャンマーへの帰還が実施されました。
実情としては、難民を受け入れる気がないバングラデシュ政府によって追い返されたロヒンギャの人々が、何の問題も解決していないミャンマーに送り返され、近年再び激しい迫害を受ける羽目になり、今度はそれが大々的な国際問題として取りざたされるようになったという経緯があります。
○ロヒンギャの武装集団の警察官殺害をきっかけに・・・
ミャンマーが軍事政権下にあった時代には世界中の人が認知していなかったロヒンギャ難民問題が、民主化に向けて国際交流が活発化すると共に明らかにされ始めましたが、2012年6月にロヒンギャと仏教徒との間に大規模な衝突事件が起こった際には、まだ国際的にはさほど問題視されることはありませんでした。
世界の厳しい目がミャンマーに注がれるようになってきたのは、2016年10月にはロヒンギャの武装集団が警察官を殺害したとして軍が大規模な掃討作戦を開始して以降です。
2017年8月には軍による大規模な虐殺が始まり、バングラデシュへのロヒンギャ難民流入が加速し、現在も何か所かの難民キャンプでの暮らしに耐えています。
バングラデシュ政府も1990年代同様に難民をミャンマーに帰還させるべく、中国の仲介を得てミャンマー政府との間で話し合いを行い、難民帰還に関する枠組みを合意した覚書に署名するまでに至りましたが、実際にロヒンギャ難民の帰還はほとんど始動していない状態です。
現状のままのミャンマーでは戻ったロヒンギャが再び迫害を受けることは明らかで、国連からもその点を指摘されていることから、難民帰還は事実上ストップしたままです。
○ロヒンギャ難民リストのすべてが帰還を拒否した
第一陣の帰還者として二千名以上のロヒンギャ難民リストが作成されたものの、その対象者のすべてが帰還を拒否したと言われ、難民キャンプでは帰還作業の開始を非難するデモが大規模に行われるまでに至りました。
ロヒンギャの人々はミャンマーでは英国統治時代以降に流入して来た不法移民といった位置づけにされているため、国籍がない状態です。
そのためミャンマーに帰還したとしても国民とは認めてもらえず、治安を脅かす存在として行動範囲が制約され、ささいなきっかけから再び虐殺が起こらないとも限らない実情があります。
国連でもロヒンギャの人々に国籍がない状態を憂慮し、現時点での難民帰還は時期尚早としています。
ロヒンギャの人々にミャンマー国籍を与えるか否かという点については現在もうやむやにされたままで、難民帰還作業は宙に浮いたままです。
バングラデシュ政府は今回も難民を完全に受け入れて定住化させることは避けたいという姿勢で、2019年以降の動向が注視されています。
バングラデシュの住民は傷つきながらミャンマーから必死に逃げてきたロヒンギャ難民に非常に同情しており、温かい救いの手を差し伸べている人も少なくありませんが、国としては決して豊かとは言えないだけに、ミャンマーへの難民帰還作業を何としても推し進めなくてはならないのが実情です。
○ゾウの絶滅にまで発展する恐れがある
ミャンマー政府もロヒンギャへの迫害を避難する世界の目によって、自国経済がひっ迫する可能性に怯えており、特に欧州連合による関税免除の適用停止が目前に迫っているといわれ、それが実行された場合には縫製加工業などの輸出競争力が低下することから、ミャンマー経済への多大なダメージが懸念されています。
人々の経済や暮らしに暗い影を落としているだけでなく、バングラデシュではアジアゾウの生息地にロヒンギャ難民が押し寄せて難民キャンプをつくったことで、ゾウの移動ルート上で難民らと遭遇したゾウが暴れて死者が出る騒ぎまで起こっています。
ゾウの大切な住処の木々が難民らによって伐採されてエサが不足する事態にまで至っており、このままの状態が続くとゾウの絶滅にまで発展する恐れがあり、人間だけの問題ではなくなりつつあります。
ミャンマーとバングラデシュだけの問題でなく、アジア全体の問題として今一度考えるべき時に来ていることは明らかです。
最終更新日 2025年12月18日 by emilyk